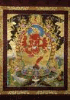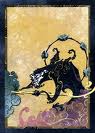 「神道」という言葉は中国の『易経』や『晋書』の中にみえるが、これらは「神(あや)しき道」という意味である。これは日本の神道観念とは性質が異なるものである。
「神道」という言葉は中国の『易経』や『晋書』の中にみえるが、これらは「神(あや)しき道」という意味である。これは日本の神道観念とは性質が異なるものである。
日本における「神道」という言葉の初見は『日本書紀』の用明天皇の条にある「天皇信佛法尊神道」(天皇、仏法を信じ、神道を尊びたまふ)である。このように、外来の宗教である仏教と対になる日本固有の信仰を指したものだった。
中国では、信仰は「鬼道」、「神道」、「真道」、「聖道」の4段階に進化すると考えられ、仏教は一番進んだ「聖道」にたっしていると信じられていた。一番下の段階が「鬼道」で、『魏志倭人伝』の中にもこの語が出てくる。次の段階が「神道」」(「神(あや)しき道」)である。すなわち、『易経』や『晋書』の中にみえる「神道」(「神(あや)しき道」)という語は、鬼道よりは進んでいるが、まだまだ劣っているという蔑称である。日本における「神道」は中国道教の「真道」「聖道」といった進化に対して保守的であり、「鬼」が蔑称文字とされても「祈祷」の字を代用するなど、他の宗教の原理主義に近い状態を維持している。
明治20年(1887年)代になると、西欧近代的な宗教概念が日本でも輸入され、宗教としての「神道」の語も定着し始める。明治30年(1897年)代には宗教学が本格的に導入され、学問上でも「神道」の語が確立した。
もともと、神道にはイエス・キリストや釈迦のようなカリスマ的創唱者が存在しなかった[3]。政権による土着の民俗信仰との支配的な祭政一致がおこなわれた神道が教義を言語で統一的に定着させなかったのは、古代より「神在随 事擧不為國」だったからであるともいわれている。そのため、外来諸教と融合しやすい性格を有することになったともいう。しかし、神道のような土着の民俗信仰と宗派宗教の併存例は世界各地でみられるものであり、日本が特に珍しい例というわけではない。
実際には、仏教公伝の当初から、廃仏派の物部氏と崇仏派の蘇我氏の間で抗争もあった。中世には、伊勢神道をはじめとして、吉田神道などの諸派が反本地垂迹説など複雑な教理の大系をつくりあげてゆく[15][16]。近世後期には、平田篤胤が、キリスト教の最後の審判の観念の影響を受けた幽明審判思想や、アメノミナカヌシを創造神とする単一神教的な観念を展開するなど近代に連なる教理の展開を遂げた。近世に大きく発展した儒家神道はしだいに大衆に支持基盤を得て尊王攘夷思想を広め、討幕の国民的原理ともなっていった。
 近代には神道事務局祭神論争という熾烈な教理闘争もあったが、結局は、政府も神道に共通する教義体系の創造の不可能性と、近代国家が復古神道的な教説によって直接に民衆を統制することの不可能性を認識して、大日本帝国憲法でも信教の自由を認めせざるを得なかった[17]。もっとも、それには欧米列強に対して日本が近代国家であることをあきらかにしなければならないという事情もあった。神社神道では教義を明確に統一できないことに由来する神道の「掴みにくさ」は、同時に、言語に強く依存した外来の諸宗教に完全には吸収同化されない、身体感覚を重視した遠い昔からの所作の現われとして現代日本社会にもなお受け継がれている。この結果、仏教や儒教、キリスト教などの受容後も、神道的なものが日本人の精神生活に幅広く残った。これらを俯瞰すると、抱擁的側面は出雲が有し、社会制御的側面を伊勢が受け持ったともいえる。
近代には神道事務局祭神論争という熾烈な教理闘争もあったが、結局は、政府も神道に共通する教義体系の創造の不可能性と、近代国家が復古神道的な教説によって直接に民衆を統制することの不可能性を認識して、大日本帝国憲法でも信教の自由を認めせざるを得なかった[17]。もっとも、それには欧米列強に対して日本が近代国家であることをあきらかにしなければならないという事情もあった。神社神道では教義を明確に統一できないことに由来する神道の「掴みにくさ」は、同時に、言語に強く依存した外来の諸宗教に完全には吸収同化されない、身体感覚を重視した遠い昔からの所作の現われとして現代日本社会にもなお受け継がれている。この結果、仏教や儒教、キリスト教などの受容後も、神道的なものが日本人の精神生活に幅広く残った。これらを俯瞰すると、抱擁的側面は出雲が有し、社会制御的側面を伊勢が受け持ったともいえる。
ウィキ から