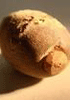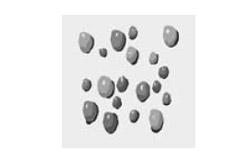 舎利とは本来「身体」を示すサンスクリット語「Sharira」に始まったものだ。そのままの音訳して「設利羅」、または意を移して霊骨と言ったりする。
舎利とは本来「身体」を示すサンスクリット語「Sharira」に始まったものだ。そのままの音訳して「設利羅」、または意を移して霊骨と言ったりする。
「金光明経」は、釈迦の言葉を借りて「舎利は定慧を磨いたものから出るので、貴重であり、舎利を得ることは上等の福田を得ること」と説明している。一説には世尊の舎利が8つの島に通じるともいわれ、俗世間の信徒たちは上人であればあるほど、入寂するとき、舎利がたくさん出ると信じる。
舎利に対する神秘な信頼は仏教の伝播とともに広く広がった。中国医薬書「本草綱目」は、舎利は羚羊の角でのみ割ることができ、かなづちでもこわれないと言った。実学者イ・ギュギョンも著書「釈典総説」で、舎利は極陰の産物なので極陽の材料であるサイの角が触れればすぐにも溶けるという話を伝える。
しかしこんな信頼に乗じて人々を惑わすことも少なくなかったようだ。「高麗史節要」には曉可という妖僧が登場する。彼は花の蜜の水と米の粉を人々に配り「すべて私の体から出た甘露舎利」と主張し、税金を増やす詐欺行為をし、忠宣王5年(1313年)に処罰された。また実学者の利益は「星湖僿說」で「舎利は昔にも得にくかったと言うのに、今は少し名前があるだけで僧侶が死んでも必ず舎利が出たと浮屠を立てる。以前は舎利の真偽をめぐり僧侶らが訴訟を起こすと、浮屠を壊して本当の舎利なのかと割ってみることもあった」と皮肉った。
初めから舎利は人間の身体の内部にあった物質が化粧時の熱によって変形されたものであるだけで、得度とは無関係だという主張もある。懐疑論者たちは1995年、国際法医学ジャーナルに人間の太股骨を摂氏1400度以上の高温で加熱したとき、水晶形態の物質が形成されるという研究が掲載されたことも指摘する。
もちろん舎利を宝物にすることは玉の価値や成分ではなく、眺める人の至極な仏心だ。ただ舎利の個数を計算して大徳の法力をん狙おうとすることは当然警戒することだ
http://japanese.joins.com から