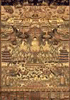古来、浄土マンダラといえば、次の三種があげられる。
古来、浄土マンダラといえば、次の三種があげられる。
(1)当麻マンダラ
大和の当麻寺で天平7年(763)に蓮糸で織りだしたと伝えられるマンダラ。
(2)智光マンダラ
元興寺に住んでいた三論宗の僧侶である智光(709−780)が感得した阿弥陀仏とその浄土を画いたもの。
(3)清海マンダラ
もと興福寺にいた法相宗の僧侶の清海(ー1017)がある老人からえた阿弥陀仏を中心にしたマンダラ。
このうち、当麻マンダラは観無量寿経の内容を詳しく画いたものである。浄土宗西山派の祖である証空が(1229)に当麻寺を訪れて感動し、それの注釈書を書き、またそれを写させて流布したために、当麻マンダラの信仰が大いに広まった。また縮小したコピーの制作もおびただしい数に上っている。
浄土三部経マンダラ
たまたま京都に長らくおられたオーストラリア出身の仏教詩人、故ハロルド・スチュアート先生(1916−1995)が1960年代後半以降、別々に京都で浄土三部経のマンダラを購入された。これを拝した稲垣が非常に感動し、1993年に浄土マンダラ研究会をつくり、その複製の流布を思い立った。その三点とは次のものである・。
(1)当麻曼陀羅
特に宇治の万福寺の第四祖になった独湛禅師(1628−1706)の讃が上部欄外に付せられていることから、「独湛曼陀羅」といわれる。原図の十六分の一で、元禄四年(1691)に摺っている。木版摺りに着色した掛け軸様式で、極彩色に純金を使っている。111x90cm。
(2)無量寿経曼陀羅
江戸時代の中末期の作と思われる。類似のものはあるが、一般にはあまり知られていない。無量寿経の内容を綿密に描き出したもの。木版摺りに着色した掛け軸様式で、極彩色に純金を使っている。
(3)阿弥陀経変相
阿弥陀経の内容を絹地に極彩色と純金を使って表している。1867年の彩色と箱書きにある。他に例を見ない逸品である。