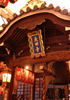「矢田のお地蔵さん」で親しまれている矢田寺(矢田山・金剛山寺)は、城下町・郡山より西へ3.5キロ、矢田丘陵の中心矢田山の中腹にあり、日本最古の延命地蔵菩薩を安置しています。
「矢田のお地蔵さん」で親しまれている矢田寺(矢田山・金剛山寺)は、城下町・郡山より西へ3.5キロ、矢田丘陵の中心矢田山の中腹にあり、日本最古の延命地蔵菩薩を安置しています。
今から約1300年前、大海人皇子(おおあまのみこ…後の天武天皇)が、壬申の乱の戦勝祈願のため矢田山に登られ、即位後の白鳳4年、智通僧上に勅せられ、七堂伽欄48カ所坊を造営されたのが当山の開基です。
当初は十一面観世音菩薩と吉祥天女を本尊としていましたが、弘仁年間に、満米上人により地蔵菩薩が安置されて以来、地蔵信仰の中心地として栄えてきました。
「矢田寺」の名で親しまれています
当山の本当の名前は、金剛山寺(コンゴウセンジ)と言いますが、「矢田寺」という名で親しまれているのは、この地が、万葉の昔より「矢田の里」と呼ばれていたことによるものです。
奈良時代の記述にも、既に「矢田寺」の名称が見られます。
境内付近一帯は、県立矢田自然公園に指定されており、矢田丘陵ハイキングコースとして、幼児からお年寄りにまで高い人気をほこっています。
また、南は斑鳩の法隆寺より、北は追分の本陣を経て霊山寺に至る古道は、山辺の道、葛城道とともに、大和のもっとも美しい道のひとつと言われています。
境内は、早春の梅にウグイスで始まり、春の桜にツツジ、初夏のアジサイの花にホトトギス、夏のキョウチクトウ、秋の萩に紅葉、晩秋初冬の山茶花まで、四季折々のおもむきを見せてくれます。
yatadera.or.jp/cont2.htm から