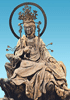日本に入った密教は真言宗(東密)と天台宗(台密)である(*5)。呪的な秘儀をするところは同じだが、その秘儀にどれだけ性的な要素があるのかわからない。ただ真言宗で重要視される理趣経では、「男女交媾の恍惚境も清浄なるぼさつの境地である」とか「男女交媾の欲望がおきるや、それは矢の飛ぶように速やかで確実である。これも清浄なぼさつの境地である」(*6)などと、性が肯定的に述べられているのである。
真言密教なのに、チベット仏教によく似た性的な行(ぎょう)を取り入れた一派があった。12世紀の初頭、仁寛が開いた立川流である(東京都の立川から興ったのでこの名で呼ばれる)。この流派は、東北と四国を除く全国に急速に広まったという。その後一時下火になったが、南北朝時代のころ文観上人が再興し大成した。
この流派は、たとえば儀式の道場を清める洒水(しゃすい)に男女の性液(セックスのときの分泌物)を使った。また仏像の前で男女が観想しつつ交合して解脱をめざしたという。チベット仏教と同じような交合する仏像も儀式に使用された。荼枳尼天(だきにてん=ダーキニー)を拝し、本尊は髑髏(どくろ)だったと言う。

立川流は、江戸時代に入ってから幕府に弾圧され消滅した。
真言宗の主流派は、「邪宗だ」として立川流を排斥した。しかし、行(ぎょう)をすることで仏様と一体になり呪的な超能力を発揮するとする点は同じである(*7)。その行(ぎょう)に性的要素が入るかどうかは、手続きが多少違うだけのことで本質的な差ではない。チベット仏教だろうと立川流だろうと、僧の行う性的行(ぎょう)は、衆生のセックスの営みとはちがい、快楽を追求するものではないのである(*8)。
チベット仏教や立川流は、解脱(げだつ)し超能力を得るための行(ぎょう)に性を利用した。だからといって、橋本峰雄も言うように、これを邪教と呼ぶべきではない(*9)。邪教とは、真言宗の主流派と争ったときに貼り付けられた攻撃のためのラベルである。いまの日本では、「性は繁殖のためにある」とする欧米のキリスト教文化が入り込んでいるから、「性を解脱に利用するなどとは邪教だ!」と叫ぶ人も多いと思う。しかし、これは自分の宗教が正当で他の宗教を邪教と見なす文化的な偏見である。かつての庶民の社会には、そもそも貞操という概念がなかったし、性は開放的だった。そして立川流は民衆に広く受け入れられ、おおいに流行したのである。この流派の教義は、当時の民衆の性に対する態度に沿ったものだったとわたしは考えている(*10)。
だれがどのようにして性が解脱に役立つという教義を密教に組み込んだものか。合理的な根拠がなくても人間は強く信仰することができる。その信仰のうえにチベット仏教はかくも緻密で壮大な体系を築いたのだ。チベット仏教の仏像を見ながら、なぜ人間はそうした認識をする脳をもつようになったのか、不思議に思った。