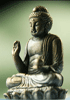[仏教に生きる]
仏壇の祭り方、お墓での参り方、お寺のお参りの方法、日常の心のありよう。ものの受け止め方。信仰者としての生き方。体験談や逸話・伝説などの共有。なにかを求め、なにかを頼りに生きるか。苦悩こそが、私たちの姿です。心が渇いています。不安です。不満足です。不安定です。だからこそ信仰でしょうか。どなたかが書いていましたが、「仏教は、哲学です。」あまりにも寛容だから、「どうしたらいいですか」という問いの答えは、「思うようにやりなさい。」「詳しく教えて」というと、「簡単でいいですよ。」そんな答えが、至極あたりまえに返ってきます。
終わりのない修行。質問するのも辛くなってきますよね。気楽に聞きたいですね。最近わかってきたのですが、「密教」とか「秘密経」とかいう『密』という文字が、不可解なイメージなのですね。「密」の意味は、「内緒」とか「仲間に入らないと教えない」のではなく、「とても重要」とか「もっとも大事」とかいう意味ですね。
どうしたらいいのでしょう。お坊さんの中には、熱心にわたしたちに教えてくださる方もおられるのですが、中には、それをチェックしてしかられる方もいます。まだまだ閉鎖的なところもあるのです。
また、素人は知る必要がないとか、深く知らないでものを言うなと諌められることもあります。まあ、昔から規則や概念を変えていくには、あくなき行動が必要ですから、疑問に思えば、後回しにしないで、すぐに調べる、聞くことですよね。

[私の仏教]
私がこんなに勉強したいと思い、その欲求が絶えない理由は、何でしょう。西国観音巡礼は、明らかに観光ドライブとスタンプラリーでした。5年かかりました。勢いあまって、西国薬師霊場めぐりのころ(今から4年あまり前)から興味が増してきて、「薬師如来」について調べだしたのです。そのころ、精神的にも衰弱するきっかけもあって、知的興味と信仰心も湧いてきて、いまに至ります。
ですから最初は薬師如来の資料からです。そして、13仏。曼荼羅から唯識。そのころからお四国遍路を始め、経典を直接読むようになり、お護摩やご真言、梵字もかじりました。やがて、念珠を買い、輪袈裟を着け、写経もそろそろ1000枚ですかね。お参りの質が変化してきました。
心の方が、あとからついてきました。ちょっと一般の方と順序が逆かもしれませんね。ですから、こうあらねばならないなんて知識先行で、自分の気持ちや感性を見直していないで、模範解答を思い込むところがありそうです。
いつの日か、思うことがそのまま仏の教えとなり、渇くことなく、すべてを許しあえる人となれますように。ぶりぶり怒ったり、不平・不満をぶつぶつこぼしたり、ああなってほしいとかこうなりたいと夢みたりしないで、流れに乗って、流されず竿ささず。すべてに感謝し、すべてを許し、穏やかで優しいひとでありたい。幸せを分け合える人でありたい。「一隅を照らす」(天台)、「いかせ、いのち」(真言)。自分だけでなく周りの人に役立てることに感謝し、労惜しまず生きていたい。
sakai.zaq.ne.jp/piicats/benkyou.htm から