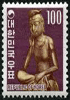実は私が日本人の夕陽信仰といったものに深い関心を持つようになったのは、韓国の仏教学者の先生から教えられたからであります。
実は私が日本人の夕陽信仰といったものに深い関心を持つようになったのは、韓国の仏教学者の先生から教えられたからであります。
今から10年前でありますが、東京で『日韓フォーラム』という国際会議があり、私も出席して日本の宗教について話をしました。それにコメントをして下さった方が李箕永先生という韓国を代表する仏教学者です。そのシンポジウムが終わりまして、最後のパーティで、その李先生と私はブドウ酒を飲みながら歓談しました。だいぶ酔っ払ってきたあたりになって、李先生が突然こういうことを言われました。
「自分は日本人がとてもうらやましい。なぜならば仏教というすばらしい宗教が、多くの日本人の心の隅々にまで浸透しているから。自分は仏教を半生研究してきたけれども、何せ韓国は儒教社会だ。だから日本人がうらやましい。」
 とこう言うんですね。私は酔っ払っておりましたけれども、はっとしました。当時の私は、全然そう思っていなかったからであります。いやとんでもない。確かに日本には仏教が伝えられたかもしれないけれども、それは頭の上のことだけだと。自分も含めて、日本人が豊かな仏教信者であるとはとても思えませんと反論したら、李先生はこう言いました。
とこう言うんですね。私は酔っ払っておりましたけれども、はっとしました。当時の私は、全然そう思っていなかったからであります。いやとんでもない。確かに日本には仏教が伝えられたかもしれないけれども、それは頭の上のことだけだと。自分も含めて、日本人が豊かな仏教信者であるとはとても思えませんと反論したら、李先生はこう言いました。
「いやいや、あなたがた日本人はあの『夕焼け小焼け』という童謡を歌うでしょう。」
これは突然のことで驚きました。酔っ払っておりましたから、実際には歌えませんでしたけれど心の中で口ずさんでみました。そのときはっと、ひょっとしたら李先生のおっしゃるとおりかもしれない、と思いました。
歌ってもいいのでありますが、今日は風邪をひいておりますので・・・では歌いましょう。(拍手)ご唱和ください。
夕焼け小焼けで 日がくれて
山のお寺の 鐘がなる
お手てつないで みなかえろ
からすといっしょに かえりましょう
どうもありがとうございました。(拍手)
この『夕焼け小焼け』を作った詩人が、中村雨紅という人であります。東京の八王子の神主の息子さんです。東京の師範学校に入り八王子と東京の間をしょっちゅう往復しておられる。お帰りになるとき八王子の西の山に沈む落日を見て、それが深い印象に残った。後に女学校の先生になって、この詩を作った。大正11年のことだったと思います。関東大震災の直前であります。
面白いことにちょうど時を同じくして、『あかとんぼ』の歌が作られているのです。これは三木露風作詞・山田耕筰作曲の名曲ですよね。 “夕焼け小焼けのあかとんぼ”であります。大正年間に作られたこの『夕焼け小焼け』と『あかとんぼ』はその後15年間続く日本の暗い時代を歌い継がれていくわけです。私はあのつらい戦争の時代、多くの日本人の心をなぐさめ、支えた歌として、この2つの曲が存在していたと思います。あまりそういうことを言う人はいませんけれども。
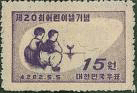 「夕焼け」というものを見たことがありますか?と私はいろいろな人に今まで聞いてきました。戦地から引き揚げ、苦難を乗り越えて日本にお帰りになった方々が異口同音に、苦難の生活の中で、いろいろな夕焼けを見て心のなぐさめを得たと目を輝かせて語り始めました。一体なぜだろうという疑問が前からございましたが、それが李先生の言葉によって、スーッと解けていくような気がしたのであります。
「夕焼け」というものを見たことがありますか?と私はいろいろな人に今まで聞いてきました。戦地から引き揚げ、苦難を乗り越えて日本にお帰りになった方々が異口同音に、苦難の生活の中で、いろいろな夕焼けを見て心のなぐさめを得たと目を輝かせて語り始めました。一体なぜだろうという疑問が前からございましたが、それが李先生の言葉によって、スーッと解けていくような気がしたのであります。