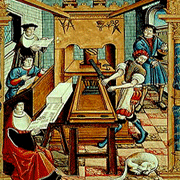 堅苦しい話は止めてちょっと歴史を繙いてみましょう。一般的に言いまして科学や技術の歴史を考えるとほとんどが西欧の歴史中心に捉えています。主なる発明や発見を思い浮かべても、その時代認識は西暦で捉えられており、日本の歴史の中でどのような時代にあったかは直感的には分かりません。例えば、ワットが蒸気機関を発明しましたのは1774年ですが、これは江戸時代の安永年間、江戸中期となります。また、有名なニュートンがどの時代かと言いますと、元禄の人となります。日本の時代感覚でいくと、明治時代くらいでもいいような気がすると思うのですが、ニュートンは実に江戸初期で、5代目将軍徳川綱吉の時代です。江戸中期にあたる時期に西欧では万有引力の法則や微分積分が考えられていたのに、日本では髷を結って、刀を差し、生類あわれみの令によって人間が処刑されていたわけです。どうして、このような差がでてきてしまったのかと申しますと、そこには宗教的な背景が有るわけです。
堅苦しい話は止めてちょっと歴史を繙いてみましょう。一般的に言いまして科学や技術の歴史を考えるとほとんどが西欧の歴史中心に捉えています。主なる発明や発見を思い浮かべても、その時代認識は西暦で捉えられており、日本の歴史の中でどのような時代にあったかは直感的には分かりません。例えば、ワットが蒸気機関を発明しましたのは1774年ですが、これは江戸時代の安永年間、江戸中期となります。また、有名なニュートンがどの時代かと言いますと、元禄の人となります。日本の時代感覚でいくと、明治時代くらいでもいいような気がすると思うのですが、ニュートンは実に江戸初期で、5代目将軍徳川綱吉の時代です。江戸中期にあたる時期に西欧では万有引力の法則や微分積分が考えられていたのに、日本では髷を結って、刀を差し、生類あわれみの令によって人間が処刑されていたわけです。どうして、このような差がでてきてしまったのかと申しますと、そこには宗教的な背景が有るわけです。
西欧文明の源流をなすのはキリスト教です。キリスト教という宗教は、神がすべてを決めて、この世の中や自然すべてを神様が造ったもの、神様の創造物で、その中で私たちが生きているという世界観があります。これは旧約聖書の考え方ですから、旧約聖書を基本としているユダヤ教、キリスト教、イスラム教も同じ世界観を共有しています。旧約聖書に「創世記」という部分があって、そこに神様がこのようにして世界を造りましたという記述があります。アダムとイブの話があるのもこの「創世記」の部分で、創造を開始してから7日目に神様がお休みを取りましたので、その日を安息日という仕事をしない日にしたのです。世界の4大宗教といえばユダヤ教、キリスト教、イスラム教と仏教ですが、そのうち3つの宗教は同じ旧約聖書を基盤としています。
その考え方の基本は決定論的です。それは神が決めて創り出した物ですから神に意志を深く考えれば解析可能と考えます。つまり、物事は解析すれば分かって数式でかけという考え方です。だから、いろいろなものを調べてどんどん記録して、記録の中から規則性を見つけだして法則性を発見し、その知識をどんどんため込むというのが彼らの方法論です。それは神の意志の理解につながる行為です。アインシュタインが一般相対性理論を美しい形をした数式として生みだしたことや神はサイコロを振らないと言って量子論を非難したことは有名ですが、その根幹には神によって生み出された調和した美しい構造を明らかにするという意図を読みとることが出来ます。
 これに対して仏教は「縁起」です。絶対者が構造を創造したのではなく、この世の構造を因果関係として捉えます。彼ありて此あり、原因があって結果があるというのが仏教の基本思想です。そして、原因には自律的原因(自己の意志決定による原因:因)と他律的原因(自分では決定することの出来ない環境条件:縁)があり、結果は多義的に決定されるという考え方です。因縁といいます。そして、この因縁論は世の中が因縁で成り立っていることを理解し、何が起こっても心が動かされないような強い自己を作り上げることが目標です。したがって、個々の事象を蓄積し解析し法則性を見いだす努力は積極的には行われませんでした。何故ならその法則性は既に明らかにされています。つまり、この世は縁起によって成り立っているということが結論です。
これに対して仏教は「縁起」です。絶対者が構造を創造したのではなく、この世の構造を因果関係として捉えます。彼ありて此あり、原因があって結果があるというのが仏教の基本思想です。そして、原因には自律的原因(自己の意志決定による原因:因)と他律的原因(自分では決定することの出来ない環境条件:縁)があり、結果は多義的に決定されるという考え方です。因縁といいます。そして、この因縁論は世の中が因縁で成り立っていることを理解し、何が起こっても心が動かされないような強い自己を作り上げることが目標です。したがって、個々の事象を蓄積し解析し法則性を見いだす努力は積極的には行われませんでした。何故ならその法則性は既に明らかにされています。つまり、この世は縁起によって成り立っているということが結論です。
一口に宗教といっても西欧の宗教と東洋の宗教では自然や世界構造に関する態度が全く異なるわけで、そのことが科学や技術に対応する方向の根本的違いを生みだしていると思います。
早稲田大学講師 今岡達雄先生 より
http://www.zenshoji.or.jp から

