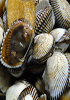私は物心ついた頃からずっと、どんな組織にも属さない一匹狼であることを自負して生きてきました。
私は物心ついた頃からずっと、どんな組織にも属さない一匹狼であることを自負して生きてきました。
そして『金の無い男は男じゃない。男にとっては金が全てだ。金さえあればこの世に怖いものは何も無い。金で人の心を買い、金で女をモノにする。金さえ持っていれば、その匂いを嗅ぎつけて人は勝手に集まってくる。狼が血の匂いに集まるように・・・。政治家であろうと、警察官であろうと、弁護士であろうと、金で転ばぬ奴はいない』というのが持論でした。
生きていくために必要なのは金だけ・・・。
ハッキリ言ってその頃の私は『道徳なんて糞食らえ!』でした。
私を変えた乞食旅
そんな私が、タイで出家する機会を得たのは13年前のこと。一日の食を乞食で得、一夜の宿を知らない寺に求めながらタイ国中を彷徨った、概ね5カ月に及ぶ旅は、私の意識を、そしてその後の人生を大きく変えました。
アッチの街からコッチの村へ、コッチの村からさらに森へと進む中、娯楽施設はもちろん、商店さえもないド田舎で何の不満も持たずに修行している若い比丘や、穴だらけの衣を纏いながらも、すべてを包み込んでくださるような優しい笑顔で私を迎えてくれた老比丘に出会いました。
私は彼らがなぜ、私にとっては人生の全てとも言えた『金も、女も、酒も』、それこそ何もない世界で、あのように満ち足りた顔をしているのか不思議に思い『ブッダとかいうおっさんは、彼らに一体何を教えたのだ』という疑念から、原始仏教の本を読み漁ったのです。
そして私は『俺が生きてこられたのは、決して自分の力ではない。今こうして生きていられるのは、多くの人たちに支えられ、助けられてきたお陰だ。俺は生きるためにどれだけの人を犠牲にしてきたのか?どれだけ多くの動植物、生きものの命を奪ってきたのか』ということに気づき、それまで知らなかった『感謝』の心を知り、人には金に代えられない大切なものがあるのだということを理解するようになったのです。
 人は自分ひとりの力で生きているのではなく、多くの縁によって生かされているのだということを実感として知ったのでした。
人は自分ひとりの力で生きているのではなく、多くの縁によって生かされているのだということを実感として知ったのでした。
もしあの乞食旅を経験しなかったら、そして『ブッタの説かれた人生の指針・哲学としての真の仏教』を学ぶことがなかったら、未だに『金さえあれば、この世で叶わないことは無い』と豪語し、心のどこかに不安を抱きながら、押し寄せてくる死の影に怯えた老後を送っていたと思います。
子供の教育は母親の胎内から
とはいえ、『道徳なんて糞食らえ!』と考えていた当時の私も、曲がりなりにも『親心』は持っていました。
十月十日もの長い間、自分のお腹の中で子供を育てる母親と比べ、父親である男性が親としての自覚を持つにいたるには、大なり小なり時間がかかるものです。
私も、産まれたばかりの娘と病院で初めて対面したとき、周りの人たちから『オメデトウ。目元がお父さんに似て可愛らしいお嬢さんですよ』と祝福されても『このシワクチャな猿のような顔したのが本当に俺の子供かいな?』という感じで、正直言って親になった感激も『俺の子だ』という実感も湧いてきませんでした。
それどころか、出産祝いにと妻の実家や友人たちからいただいたお金を『こりゃ有り難い。臨時収入だ!』と言わんばかりに、毎晩飲み歩く始末・・・。
そんなエエカゲンな親でしたが、娘が成長するにつれ、可愛くって可愛くって仕方なくなり『俺は親としては自信も資格もないが、この子の成長に合わせ、この子に恥ずかしくないように、この子と一緒に成長し、この子の一番の親友として良き相談相手になりたい』と思うようになりました。
また、『自分の娘が俺のような道徳を無視した男に犯されたらどうする? 息子が俺のような無法者に絡まれ殺されでもしたらどうする?』そんなことを考え出したころから、社会秩序の必要性を考えるようにもなりました。
しかし、やはり私の子供たちが立派に育ってくれたのは、母である別れた妻の力が大きい。というよりむしろ、すべて彼女のお陰だと言ったほうが正しいでしょう。
私の話は極端な例だとしても、一般に、子供に与える影響は父親からより母親からのほうが大きいと私は思います。
特に、ただ食べさせ、学校教育を受けさせるだけではない、本当の意味での子育て、子供の教育、道徳心や慈しみの心を育てるためには、女性の力が重要であり、欠かせないと・・・。
私たち人間は、まず母親を真似て母親を手本に社会に適応する智恵をつけていきます。ものごとの善悪を判断する基礎は、母から教わるのです。『これを触っては危険だ』とか、『これを口に入れてはいけない』とか『この行為はしてはいけない』とか言う、人間として社会の中で生きていく上で欠かせない判断の基礎的知識や、道徳心、慈しみの心などはまず母から学ぶのです。
それは生まれてきてからだけではないのです。母親の胎内にいるときから、もっと厳密に言えば性行為により精子と卵子が結びついた瞬間から『生』が始まり、その時点から母親を通じ、人間として生きるための知識を吸収しながら成長するのです。母が耳で聞き、眼で見て、皮膚で感じ、頭で判断することは、すべてお腹の子に伝わっているのです。
子供の教育とは、子供が産まれ出てきてから始まるのではありません。母親のお腹に宿った瞬間から始まるのです。
それ故に子育て中の女性は、心身ともに健全で安らかな日々を過ごす必要があり、子の父親である男性は、子育て中の女性が平安で健やかに育児に専念できるよう、護っていかねばなりません。それが父親としての子育ての責任と義務だと私は思っています。
昨今、日本中で大きな社会問題となっている未成年の凶悪犯罪、虐め問題や登校拒否児童、引きこもり青年の増加etc・・・。
これらは刑法や教育基本法等の小手先だけの法律改正や、教育カリキュラムの見直しだけでは決して解決しません。
これらの因はすべて日本人全体の道徳心の欠如にあるのではないかというのが、私の考えです。
アメリカの占領政策による押し付けもあったでしょうが、我々の世代の日本人はあの敗戦によって宗教を捨てると同時に、日本人が先祖より受け継いできた、日本人としての拠り所である道徳をも捨ててしまいました。
その結果、経済的成長を旗印に『世界に追いつけ追い越せ』と経済大国に発展し、私たちの子供の時分から比べれば、確かに欲しいものは概ね何でも手に入るし、生活全般も著しく豊かになりました。
 しかし、その見返りとして『失ったものも大きかった』のは、誰もが否定できない事実だと思います。日本丸の舵を取るべき政治家や官公庁の役人の不正、腐敗。それを取り締まるべき警察による相次ぐ不祥事の発覚。自分の企業さえ良ければという恥知らずの企業犯罪。返済能力や担保価値を充分審査せず、預金者の大切なお金を貸し出し、多額の不良債権を抱え込んで日本経済を破綻寸前にまで追い込んだ挙句に、国民の貴重な税金で後始末をして貰い、その責任をも取ろうとしない銀行をはじめとする金融機関・・・。
しかし、その見返りとして『失ったものも大きかった』のは、誰もが否定できない事実だと思います。日本丸の舵を取るべき政治家や官公庁の役人の不正、腐敗。それを取り締まるべき警察による相次ぐ不祥事の発覚。自分の企業さえ良ければという恥知らずの企業犯罪。返済能力や担保価値を充分審査せず、預金者の大切なお金を貸し出し、多額の不良債権を抱え込んで日本経済を破綻寸前にまで追い込んだ挙句に、国民の貴重な税金で後始末をして貰い、その責任をも取ろうとしない銀行をはじめとする金融機関・・・。
これは日本人全体の道徳心がマヒしているから起こったことではないでしょうか? 今こそ世界の中の日本として『世界に通じる新しい日本の道徳』を育て上げ、次代を背負う子供たちに伝えていかなければならない時ではないでしょうか?
現在子育てに奮戦中の親御さんはもちろん、将来子供を持つ可能性のある夫婦も、あるいは子供に恵まれなかったという人も、日本中の男性も女性も皆が『私たちが次代の日本を背負う人間を育て上げるのだ』という意識と誇りを持って、自分の子供だけではなく、他人の子供でも『善い事は善いと誉め、悪いことは悪いと叱り』、恥ずかしながら我々世代が捨て、失い、忘れてしまった道徳心を、次代の子供たちに植え付け『道徳心に満ちた、世界に通用する次代の日本人』を育てていって貰わなければならないのです。
これは簡単そうで難しいことです。子供は口先で言っただけでは聞きません。まず大人が道徳を踏まえた、子供の見本になるような言動をしなければならないのですから・・・。そのためには、まず大人が道徳を学び、考える必要があると思います。
道徳と利他の心
動物の世界にもその世界の秩序を護るために、掟があります。たとえば、犬同士が激しい喧嘩をしても、相手の前に腹を見せ、仰向けになって負けを認めれば、もうそれ以上攻撃はしないのです。
人間も動物も、単独で生きていけるなら掟もいらないでしょう。しかし集団でしか生きていけない動物にとっては、掟が存在してはじめて秩序が保てるのです。我々人間社会も『これを犯したらこの罰を与える』という法以前に、社会生活を円滑にし、皆が安心して生きていけるための道徳が必要です。
 では、『道徳』とは何でしょうか? 私はこの問いに対する明確な答えを持っていません。しかし仏教でいうところの『利他の心=他の人に利益を与えたいという心』、これが『道徳』とは何かということを考える時の根源だと思っています。
では、『道徳』とは何でしょうか? 私はこの問いに対する明確な答えを持っていません。しかし仏教でいうところの『利他の心=他の人に利益を与えたいという心』、これが『道徳』とは何かということを考える時の根源だと思っています。
ブッダは、『あたかも、母が己が独り子を命を賭けても護るように、そのように一切の生きとし生きるものどもに対して無量の慈しみ心を起こすべし。また全世界に対して無量の慈しみの意(こころ)を起こすべし。上に、下に、また横に、障害なく怨みなく敵意なき慈しみを行うべし』と説かれています。(経集第一章149・150)。
また、『どの方向に心でさがし求めてみても、自分よりさらに愛しいものをどこにも見だせなかった。そのように、他人にとってもそれぞれ自己が愛しいのである。それ故に、自分のために他人を害してはならない』という言葉も残されています。(ウダーナヴァルガ第五章18)。
つまり、『母親が我が子に抱くような慈しみの心を持って他人と接する。自分が言われて嫌な言葉や、されて嫌なことは他人にしない。自分が言われて嬉しいことや喜ばしい言葉を他人に施す』ということではないかと私は捉えています。
哲学者の梅原猛さんや、京セラを産み育て上げた稲盛和夫さんは、『宗教的な裏づけのない道徳はありえない』と、その著書で主張されています。私は、『ブッタの説かれた人生の指針・哲学としての真の仏教』を学ぶことで『道徳』を考えるようになりました。
だからといって、私は『仏教徒になれ』と強制するつもりは、毛頭ありません。ただ『宗教はチョット・・・』と毛嫌いせず、世界の多くの人々が『人生の指針・日々の生活の中での判断基準・拠りどころ』としている世界的宗教(キリスト教、イスラム教、ヒンズー教や、葬式や観光仏教でない真の仏教、それに中国や韓国の人々の心の底に今も生きている儒教など)と言われるものを学び、その教えの中から何かを掴んでもらえればと思っているのです。
世界の人たちと仲良く肩を並べ、日本人ではなく世界人として、世界に通じる未来の日本人を育てるために・・・。
『ものごとは心にもとづき、心を主とし、心によってつくり出される。もし汚れた心で話したり行ったりするならば、苦しみはその人につき従う。…車を引く牛の足跡に車輪がついていくように』法句経第一章の1
『怒りやすく怨みを抱き、邪悪にして、見せかけであざむき、誤った見解を奉じ、たくらみのある人、……かれを賎しい人であると知れ』経集第一章116
『みずからは豊かで楽に暮らしているのに、年老いて衰えた母や父を養わない人がいる、…これは破滅への門である』経集第一章98
『父母につかえること、妻子を愛し護ること、仕事に秩序あり混乱さぬこと、……これがこよなき幸せである』経集第一章262
http://omoroibouz.exblog.jp/4213411/ から