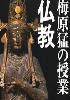梅原 猛(うめはら たけし、1925年3月20日 – )は、日本の哲学者。京都市立芸術大学名誉教授、国際日本文化研究センター名誉教授。京都市名誉市民。文化勲章受章者。梅原日本学と呼ばれる独自の世界を開拓し、またスーパー歌舞伎を創作するなど、幅広い活動を行っている。
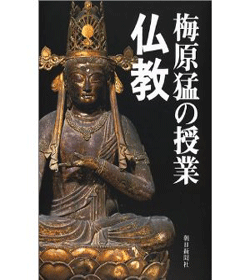 愛知県知多郡で育つ。乳児期に実母(石川千代)を亡くし、生後一年九ヶ月で伯父夫婦(梅原半兵衛・俊)に引き取られ養子となる。実父は当時東北大学の学生だった梅原半二。小学校の頃は遊んでばかりいて空想好きのために勉強に身が入らず、愛知一中の入試に失敗している。
愛知県知多郡で育つ。乳児期に実母(石川千代)を亡くし、生後一年九ヶ月で伯父夫婦(梅原半兵衛・俊)に引き取られ養子となる。実父は当時東北大学の学生だった梅原半二。小学校の頃は遊んでばかりいて空想好きのために勉強に身が入らず、愛知一中の入試に失敗している。
私立東海中学に辛うじて入学。南知多町(当時は内海町)の実家から2時間半をかけて通学した。1942年、広島高等師範学校に入学するが二ヶ月で退学、翌年第八高等学校入学。
青年期には西田幾多郎・田辺元の哲学に強く惹かれて、大学進学に際しては東大倫理学科の和辻哲郎(東大赴任前は京大哲学科の西田の下で助教授であった)の下で学ぶか、あるいは京大哲学科の西田の下で学ぶかの選択に迷ったが、結局、1945年、京都帝国大学文学部哲学科に入学する。が、その年田辺は退官していた。西田も、すでに1928年に京大を退職していたが、京大哲学科には西田の影響が存在すると考えた。父親は哲学科への進学を歓迎しなかったが、梅原の熱意が強いため許可した。入学直後、徴兵され、9月復学。1948年、同大を卒業。
大学院では山内得立、田中美知太郎に師事、ハイデッガー哲学に惹かれつつもギリシャ哲学を専攻、しかし二度にわたって田中と対立した。最初の論文「闇のパトス」(1951年)は、哲学論文の体裁をとっておらず甚だ不評だったが、のちに著作集第一巻の表題となる。二十代後半、強い虚無感に襲われて、賭博にのめりこむような破滅的な日々を送り、1951年、養母・俊の勧めでピアニストの夫人と結婚、同年、長女が生まれた時、ヘラクレイトスについての論文を書いており、「日の満ちる里」という意味でひまりと名づける。のちヴァイオリニストとなった。そしてハイデッガーの虚無思想を乗り越えるべく「笑い」の研究に入り、いくつかの論文を発表したが、これは完成しなかった。30代後半から日本の古典美学への関心を強め、「壬生忠岑『和歌体十種』について」(1963年)という論文を書く。
最近は精力的に神道・仏教を研究している。NHKテレビの生放送中に薬師寺管長の橋本凝胤と「唯識」をめぐり、大激論を交わす。
京都若王子(京都市左京区、哲学の道近辺)の和辻哲郎旧邸に住む。
日本仏教を中心に置いて日本人の精神性を研究する。西洋哲学、西洋文明に対しては否定的な姿勢をとる。西洋哲学の研究者が多い日本の哲学者のなかで、異色の存在である。市川猿之助劇団のために『ヤマトタケル』や『オオクニヌシ』『オグリ』などの歌舞伎台本を書き、これが古典芸能化した近代歌舞伎の殻を破ったので、スーパー歌舞伎と呼ばれている。また『ギルガメシュ叙事詩』を戯曲化した『ギルガメシュ』は中国の劇団が上演し、中国の環境問題の啓蒙に大きな役割を果たしている。『中世小説集』や『もののかたり』など説話に基づく短編小説集も評判をとっている。また『王様と恐竜』『ムツゴロウ』『クローン人間ナマシマ』などのスーパー狂言の台本も書いている。九条の会の呼びかけ人の一人。平城遷都1300年記念事業特別顧問。2006年には源氏物語千年紀のよびかけ人となる。
鈴木大拙を近代日本最大の仏教者と位置付け、その非戦論の重要性を訴える。また「梅原日本学」と呼ばれる一連の論考では飛鳥時代の大和朝廷の権力闘争を追求するなど、日本思想や日本古代史への興味は強烈である。天皇制への支持は強いが、排外的ナショナリズムには批判的であり、靖国神社や憲法改正には否定的な立場を採る。イデオロギーの学術への介入それ自体を批判している。なお、1991年には召人として皇居歌会始に出席している。
また、熱烈な多神教優越主義者、反一神教主義者で、多神教は一神教より本質的に『寛容であり優れている』と主張しており、続けて多神教が主流である日本文化の優越性を説いている。その説は多くの「日本文化の優越を語る日本人論」に影響を与え、そのため梅原は、中曽根康弘が創設を主導した「国際日本文化研究センター」の初代所長に就任することになる。
あわせて、臓器移植反対論者として知られている。
日本漢字能力検定協会の大久保理事長に依頼され、約10年に渡って同協会の評議員を勤めていたが、その間、会議出席などの評議員としての活動を全く行っていなかった。2009年に発覚した協会運営問題に際し、このことについて「信用したことを後悔している。関連会社への委託などとんでもないことで、評議員の機能を果たせなかった自分への怒りも感じる」と弁解した。
ウィキ から