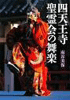6世紀の末、推古天皇の御代に皇太子として摂政の地位に就かれた聖徳太子は、篤く仏教に帰依され、その興隆弘通を図られました。太子は当時、仏教と共に我国に伝来した舞である伎楽(ぎがく)も仏教儀式に不可欠の荘厳として、楽人(がくにん)を召してこれを伝習せしめました。後にこの伎楽は、現在の舞楽に吸収されることになります。さてこの時、伎楽を伝習すべく召された楽人たちは、聖徳太子の重臣秦河勝(はたのかわかつ)の息子や孫であったとされ、この河勝末裔たちが四天王寺において活躍する天王寺楽人になったといわれています。
6世紀の末、推古天皇の御代に皇太子として摂政の地位に就かれた聖徳太子は、篤く仏教に帰依され、その興隆弘通を図られました。太子は当時、仏教と共に我国に伝来した舞である伎楽(ぎがく)も仏教儀式に不可欠の荘厳として、楽人(がくにん)を召してこれを伝習せしめました。後にこの伎楽は、現在の舞楽に吸収されることになります。さてこの時、伎楽を伝習すべく召された楽人たちは、聖徳太子の重臣秦河勝(はたのかわかつ)の息子や孫であったとされ、この河勝末裔たちが四天王寺において活躍する天王寺楽人になったといわれています。
平安時代においては、都の貴族の四天王寺詣の楽しみのひとつともなっていたほどの天王寺舞楽の伝統を担い続けた天王寺楽人たちは、江戸時代になると、京都・奈良の楽人と共に官位・官禄を賜る三方楽所の楽人となり、宮中での活躍の場も与えられましたが、四天王寺における聖霊会をはじめとする舞楽法要の伝統も併せて守り継いできました。四天王寺では、今日においてもなお、天王寺楽人の伝統を引き継いだ「雅亮会」(がりょうかい)の協力によって一千数百年の歴史を誇る古式ゆかしい舞楽法要が執り行われ、 聖霊会の舞楽は重要無形民俗文化財に指定されています。
聖霊会舞楽大法要
4月22日 午後1時六時堂前石舞台
聖徳太子のご命日(本来は旧暦の2月22日)にご聖霊を慰めるために行われる舞楽法要です。
篝の舞楽
8月4日 午後7時
伽藍内講堂前 夕刻より篝火の中、平安朝絵巻を再現する舞楽が奏され、広く一般に公開されています。
経供養
10月22日 午後1時
聖霊院前 古来は非公開でしたが、現在は公開されており『椽の下の舞』として親しまれています。