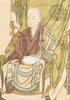法然の開いた浄土宗が、一般の民衆に受け入れられていたころ、栄西が中国から伝えた臨済宗が、武士を中心に広まっていました。ただ、栄西の伝えたものは禅だけでなく、天台宗や密教の教えもあったので、正式に臨済宗が伝えられたのは、のちに中国から直接来日した禅僧たちによってです。
法然の開いた浄土宗が、一般の民衆に受け入れられていたころ、栄西が中国から伝えた臨済宗が、武士を中心に広まっていました。ただ、栄西の伝えたものは禅だけでなく、天台宗や密教の教えもあったので、正式に臨済宗が伝えられたのは、のちに中国から直接来日した禅僧たちによってです。
臨済宗の教えは、「自分をぬきにしてさとりを得ることはできない」というものです。なにかよそに「ありがたいもの」があると思って、かんじんの自分を見失ってはならないということです。「自分を知る」ことは、簡単なようでなかなか難しいものです。たとえ分かっているつもりでも、それは自分の一面でしかありません。そういう「自分の中にある、自分でも気づかない本当の自分」に気づくことが、臨済宗の教えの根本にあります。
鎌倉時代に日本に伝えられた、もう一つの禅宗である曹洞宗は、道元によって伝えられました。道元は、単純に中国の曹洞宗を伝えたのではなく、お釈迦さまからつづく「正しい教え」を伝えようとしました。
曹洞宗の教えは、余計なことを考えずに、ひたすら坐禅をすることで、その姿がそのまま「ほとけ」の姿なのだ、というものです。道元は、さとりを得ることも「雑念」と考えました。その深い考えは『正法眼蔵』という書に記されています。
 臨済宗や曹洞宗などの禅宗では、日常の生活のすべてが修行であると考えられており、坐禅だけでなく、そうじや草取りなども重んじています。臨済宗と曹洞宗のちがいは、坐禅に対する考え方のちがいです。臨済宗では「公案」という、いわゆる禅問答によって「本当の自分」を見つけるために坐禅をするのに対して、曹洞宗では、坐禅をしているその人自身が、すでに「本当の自分」であると考えているのです。
臨済宗や曹洞宗などの禅宗では、日常の生活のすべてが修行であると考えられており、坐禅だけでなく、そうじや草取りなども重んじています。臨済宗と曹洞宗のちがいは、坐禅に対する考え方のちがいです。臨済宗では「公案」という、いわゆる禅問答によって「本当の自分」を見つけるために坐禅をするのに対して、曹洞宗では、坐禅をしているその人自身が、すでに「本当の自分」であると考えているのです。