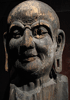六世紀末、隋王朝が中国を統一した。そして短命に終わった隋に次いで七~一〇世紀に東アジア全体に勢力を拡大したのが唐王朝であった。この時代は様々な宗派が相次いで誕生し、それらの論争も華々しく繰り広げられ、中国仏教史の絶頂の時代であった。
詳しくみてみよう。北周の武帝の廃仏(五七四年)ののち、仏教を復興させたのは隋の文帝(在位五八一~六〇四年)である。文帝は都の長安に大興善 寺を建て、全国に舎利塔を建立した。文帝を継いだ煬帝(在位六〇四~六一八年)は慧日道場などの四道場を建立し、また天台宗の開祖、智(五三八~五九七 年)を支持した。
隋代の宗派には三論宗、天台宗、三階教などがある。『中論』『十二門論』『百論』の三つの論に基づいて成立した三論宗は、吉蔵(五四九~六二三 年)によって大成され、高句麗や日本に伝えられた。天台宗は慧文、慧思と相承し、智?が大成した宗派である。また、当時の末法思想の流行のもとに成立した のが信行(五四〇~五九四年)を開祖とする三階教である。
隋を継いだ唐の仏教は、東アジア全域に伝播し、渤海・朝鮮・日本・ベトナムを包括する東アジア仏教圏を形成した。唐の則天武后から玄宗の時代にかけて、大雲寺・竜興寺・開元寺などの官寺が全国に建立されたが、この制度は日本に伝わり国分寺となった。
玄奘など訳経僧の活躍

唐代の訳経僧でもっとも有名なのが玄奘(六〇二~六六四年)である。玄奘が翻訳した『成唯識論』によって成立したのが法相宗である。弟子の基(慈 恩大師、六三二~六八二年)が開祖とされる。法相宗の教理の中で中国仏教全体に大きな影響を与えたのが五性各別説であった。これは人が悟れる能力に五つの 区別を設けるものであり、なかには悟れない者がいる、という主張であった。それまでの中国仏教では、すべての者が悟れることを疑わなかったが、当時の最先 端の学説に基づく五性各別説に反論するのは容易ではなかった。
この学説に対して反論した代表的な人物が、華厳宗を大成した法蔵(六四三~七一二年)である。杜順、智儼につぐ三祖・法蔵が大成した華厳宗は、 『華厳経』に基づき南北朝時代の地論宗を受けて成立した宗派であった。法蔵は、法相宗の立場を自分の教学の中に取り込みつつ、それを超える原理を提示して 五性各別説を克服した。
その他、密教は、ともにインド出身の善無畏(六三七~七三五年)が『大日経』を、金剛智(六七一~七四一年)が『金剛頂経』を訳出し、さらにイン ド渡航も果たした不空三蔵(七〇五~七七四年)により大成された。そして、不空に学んだ恵果(七四六~八〇五年)の弟子、空海により密教が日本に伝えら れ、発展することになる。玄奘の訳経を助けた道宣(五九六~六六七年)は四分律宗を成立させたほか『続高僧伝』を著した。道宣の系統を継ぐ鑑真は日本に律 宗を伝えた。
また達磨(五世紀後半~六世紀前半)を開祖とする禅宗は六祖の慧能(六三八~七一三年)によって独立し、その後、南宗・北宗などに分かれて、中国 仏教の主流となった。曇鸞(四七六?~五四二?年)によって開かれた中国浄土教は道綽(五六二~六四五年)、善導(六一三~六八一年)によって宗派として 確立した。とくに、善導の浄土教は日本の浄土教、なかでも法然(浄土宗)に大きな影響を与えた。
総じて隋・唐代の仏教こそが中国仏教の完成形態であり、日本などの周辺地域の仏教に与えた影響も大きいものがあった。
(文・佐藤 厚 さとう・あつし 一九六七年、山形県生まれ。専門はインド哲学・仏教史。東洋大学非常勤講師)
todaibussei.or.jp/asahi_buddhism/18.html から